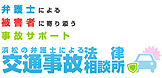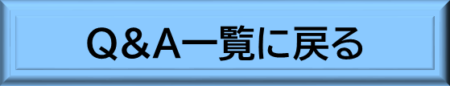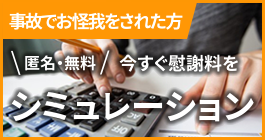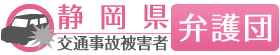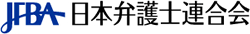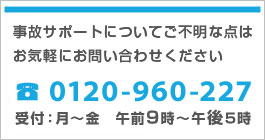Q②-13:家事従事者の休業損害
Q:仕事をしておらず、家事を行ういわゆる家事従事者が交通事故に遭い、怪我の痛みや治療のために、ほとんど家事ができていないような場合にも、特別な損害の請求はできないのでしょうか?
A:家事従事者として、休業損害を請求することが可能です。

家族のために家事をしている家事従事者については、家事労働を評価し、現金収入がなくとも休業損害を請求することができます。このような休業損害を通称「主婦(夫)休損」といいます。「誰かしらのために」家事をすることで、他人の財産上の利益を生み出している(例えば、妻が家事を行うことで、夫は安心して仕事に専念できる)と評価される場合に損害が認められるため、1人暮らしの場合には、家事従事者としての休業損害は発生しません。しかし、ひとり暮らしの場合に、家事ができなくなることにより家政婦などに家事を依頼した際は、その費用を損害として請求できる可能性があります。
1.算出のベース
休損のベースとなる収入額(基礎収入)ですが、厚生労働省が毎年実施する「賃金構造基本統計調査」により結果に基づいた平均収入(賃金センサス)を用います。通常は、性別ごとの全年齢平均賃金を用いることが多いのですが、高齢家事従事者の場合には、現実の収入額について全年齢との乖離があると考えられることから、対象の年齢別平均賃金を利用して計算する場合があります。
2.計算方法
では、実際にどのように休損額を計算していくかですが、主に以下の2通りがあります。
①逓減法(ていげんほう)
怪我や、通院及び治療による家事労働への支障割合をパーセンテージで表す方法です。例えば、受傷初期に、強い痛みが伴い全く家事ができなかった場合は支障割合100%、少しずつ快方に向かっているものの、半分程度家事が行えていないと感じる場合には50%、治るにつれて結構できるようになれば25%、…というように表し、前述の基礎収入をもとにした日額に、そのパーセンテージを掛け合わせることで損害額を計算します。
この方法は、被害者自身がその時々でどの程度の支障割合があったかをそれなりに記録しなければならない上、計算の手間がかなりかかります。
②通院日ベース計算
治療のために通院した日は家事が全くできなかった(家事を休業した)とみなし、日額と通院日を掛け合わせて休業損害を計算する方法です。実際には、通院日に家事を全くしなかったかと言われるとそうではない場合がほとんどだと思われますが、逓減法での計算にかかる手間を考えた時に、通院日ベースで計算をすることで、ある程度同じような結果が出るだろうという期待のもとで用いられています。
3.主婦(夫)休損はフィクションの議論である
主婦(夫)休損というものが、「現実収入が無くとも家事労働を評価して現金化する」という考え方ですから、かなりフィクション寄りの議論ではあります。例えば、令和4年度の女性全学歴全年齢平均の年収は394万3500円であると発表されていますが、世の主婦業を営む方々が一律この年収と同等に稼働しているかといわれると、色々な意見があるでしょう(ただ、実際に主婦休損を計算する時には、この数字を年収として日額を算出するのです)。しかしながら、裁判実務においても、家事従事者については、現実の現金収入が無くともその家事労働を評価し、家事労働ができなかったあるいは支障があった期間については、家事従事者として相応の休損が認められ得るということはごく当たり前となっています。
また、兼業主婦(夫)の場合、現実の仕事に休業が生じていなければ休業損害は原則認められません。しかし、主婦(夫)業への影響があった場合、主婦(夫)休損に切り替えて請求できる可能性があります。これにより、休損の請求額をかなり大きくできる場合があります。
なお、上記の逓減法の計算は、現実離れしない程度にパーセンテージを操作することもできるので、柔軟な考えが肝要ですが、後遺障害等級第14級9号の労働能力喪失率が5%ですので、例えば、後遺障害が認定されていないにも関わらず、逓減法にもとづくパーセンテージを5%より大きく設定するような場合は、認められない可能性が高いと思った方がよいでしょう。
交通事故の怪我で家事労働への影響が出てしまっている方で、休業損害の請求をお悩みの方は、ぜひ一度弁護士への相談をご検討ください。