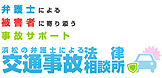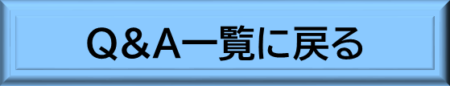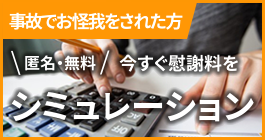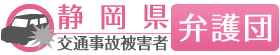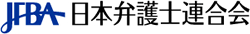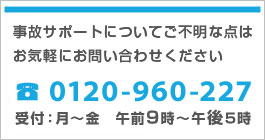Q②-9:「その程度の事故なら怪我しない」?
Q:車を運転していて信号待ちをしている最中に、突然前方の車がバックして追突してきました。むち打ちで通院したいのですが、相手の保険会社から「低速度での追突だから、怪我をするのは有り得ない。治療費は支払えない。」と言われてしまいました。このような場合、どうすればよいでしょうか。
A:受傷の妥当性を後に争うこととなります。裁判はほぼ必須となりますが、解決するまでは自己負担は免れないので、健康保険(場合によっては労災保険)等を利用し、自己負担額を抑えるようにしましょう。
このようなケースは、通称「受傷疑義案件」と呼ばれ、簡単に言えば加害者側から「本当に怪我をしたのか、事故との因果関係があるのか」と疑われるケースです。基本的には、加害者側(主には加害者側の保険会社等)が主張するケースが多いですが、自賠責への事前認定や被害者請求時に自賠責が受傷関係を否定した場合にも受傷疑義案件として発展する可能性があります。
1.受傷疑義案件の態様
受傷疑義をかけられやすい案件としては、どのようなものがあるでしょうか。
①事故の衝撃が軽度と捉えられるもの
- 逆追突
- 低速での追突事故
- ミラー同士の接触
- ドアパンチ
などがあります。いずれも、軽度の衝撃と捉えられることから受傷の有無が争われやすいのです。
②事故態様に対して重篤な症状や後遺障害が残っているもの
事故自体で被害者本人に加わった衝撃はそこまで激しいと言えないにも関わらず、重篤な神経症状などが残ったような場合です。加齢に伴う脊柱管狭窄やヘルニアなどですでに神経への異常を来しかけていたところに、事故の衝撃で重篤な神経症状が発現するようなケースがあります。なお、このような場合は、事故と怪我の因果関係の否定とまではいかなかったとしても、本人の持病が傷害に影響を与えたとして素因減額がなされやすい傾向にあります。
③事故後の通院や症状の訴えから発展するもの
受傷疑義案件としてあり得るケースとして、事故後の通院頻度や、症状の訴えの矛盾などで加害者側が受傷疑義を主張するものがあります。
例えば、
- 事故後相当期間が経ってから通院を開始したケース
⇒一般的に、整形外科的な症状は、受傷後間もない頃に症状が強く出やすい傾向にあるため、「事故直後に通院しなかった=怪我をしなかった」と決めつけられやすく、その後の通院については因果関係を否定されがちです。 - 事故後相当期間が経ってから別の部位の痛みを訴えたケース
⇒ほぼ同様ですが、通院後しばらくしてから別部位の痛みや症状を訴えた場合、その部分については因果関係を否定されがちです。
2.受傷疑義案件への対応の仕方
では、こういった案件については、どのように対処していくと良いでしょうか。
①人身傷害保険・健康保険等で対応する
加害者側(の保険会社)が受傷を否定する場合、治療費等の一括対応はしてもらえません。つまり、後に加害者側に請求するにしても一旦被害者側で立て替えなければいけないのです。
そのような場合に有用なのが人身傷害保険です。被害者自身の自動車保険に任意で付けるものではありますが、自身が被害者か加害者かはたまた自損事故かを問わず、交通事故で負った怪我について自分の保険会社が治療費等を支払ってくれます。なので、受傷疑義案件となり加害者側が治療費の支払いを拒否するような場合には利用するとよいでしょう。治療費等だけでなく、休業損害や慰謝料・後遺障害に関する補償も行ってくれますが、支払いは人身傷害保険の基準で支払われるため、実際の損害額との差がある場合には、その差額は加害者側に請求していくことになります。
人身傷害保険が無い場合には、いよいよ被害者側で立て替えるしかありません。治療費を抑えるためにも、健康保険等(労災の場合は労災保険)を必ず使用しましょう。
②きちんと病院(特に整形外科)に行く
態様の中でも説明しましたが、受傷疑義案件の中には、事故後から初回の通院までに期間が空いてしまっているがために、加害者側から受傷や一括対応を否定されてしまうケースもあります。なので、事故後少しでも違和感を感じる場合には、ためらわず病院に行って医師の診察を受けましょう。中途半端に我慢することが1番の損です。なお、接骨院・整骨院・整体院(以下「接骨院等」といいます)への通院を好む方がいますが、接骨院等で施術を行う方たちは医師では無く、厳密に言えば治療(医療行為)ではないため、接骨院等への通院のみ継続し、病院(整形外科等)への通院は全く行わないような場合にも、加害者側は治療費の支払い等を否定してきますので、必ず整形外科等への定期的な通院も行いましょう。
③自らが感じる症状は正直にきちんと伝える
この点もすでに説明していますが、通院開始後しばらく経ってから別部位の痛みや症状などを訴えた場合、その点については因果関係を否定されてしまいがちです。その点では、初診時に、自らが感じている症状・痛み・違和感などはきちんと医師に伝えることが重要です。患者が医師に伝えたことは、原則カルテに明記されるため、後に重要な証拠となります。また、特に事故自体が軽度の衝撃であるとして受傷疑義へと発展する場合、被害者の自覚症状(愁訴)に頼らざるを得ない場合も多くあります。その場合、被害者自身の症状や訴えの一貫性があるかも重要となります。決して嘘はよくありませんが、診察の際には、自分が感じている症状は正直にきちんと伝えるようにしましょう。
3.裁判での状況
裁判で争われる場合には、カルテ・双方の速度が記された実況見分調書・物損に関わる資料などが判断材料となります。また、双方から工学的な鑑定書(事故車両の損傷状況や、事故現場に残る痕跡、受傷状況など、様々な要素を工学的に分析・検証し、当時の事故状況を部分解明するもの)が提出されることもあり、それらの証拠に対する反論主張が重ねられます。工学的な鑑定書については、単に一般論を述べるだけでは足らず、具体的事案についての言及がなされているかが重要です。
なお、裁判の多くは和解で終了しますが、判決までいく場合もあり、結果としては受傷を否定した判決も一定程度存在するという状況です。
①受傷を肯定する意見
- 頸椎の過伸展(衝撃によって身体が鞭のようにしなること)を抑制するために開発されたヘッドレストが義務化されていても、依然として頚部受傷者が増加していることは知られており、むち打ち損傷のメカニズムが医学的には解明されていない。
- 頸椎捻挫は画像所見がないことがほとんどであり、被害者の自己申告にならざるを得ない。低速の追突事故でも頸椎捻挫は珍しくないし、医学的に否定することも難しい。
②受傷を否定する意見
- 頸椎捻挫の発生機序は頚椎の過屈曲と過伸展であり、鞭のようにしなることで生じるものだが、低速事故ではこれが生じない。
- 捻挫は画像所見が無く、あくまで自覚症状(愁訴)のみに基づいている。したがって、愁訴の信用性の問題となる。
「このような主張をすれば絶対認められる」というものはありませんので、案件ごとの細かな事故態様や各種資料から、因果関係の存在や受傷を粘り強く主張していくことが重要です。
非常に困難な案件になると思いますので、実際にお困りの方は、弁護士への相談をご検討ください。